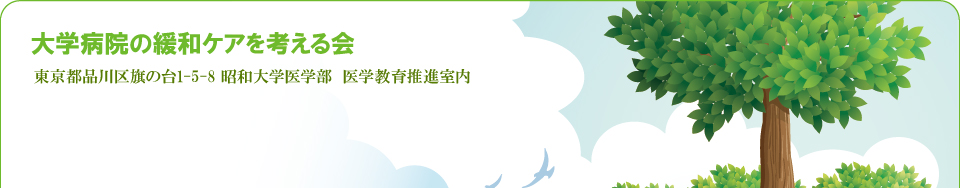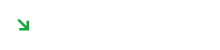
メールアドレスを入力し、登録ボタンを押してください。ホームページが更新された際に、登録アドレスに通知が届きます。

2025年度「第12回医学生の緩和ケア教育のための授業実践大会」のご案内です。お申し込みは、ポスターのQRコードより必要事項を御入力ください。多くのご参加をお待ちしております。
![]()
![]()
「リハビリ」と聞くと「機能回復による社会復帰」に辿り着く。ところがその起源は「名誉回復」である。死は誰にでも訪れるが、意識され難い。進行がんや難病は、診断確定からその影がチラつく。
この場面でリハビリは、弱者に寄り添い、快さを共有できることである。そんな死の臨床のリハビリを一緒に学びませんか。
この場面でリハビリは、弱者に寄り添い、快さを共有できることである。そんな死の臨床のリハビリを一緒に学びませんか。
| 日時 | 2025年11月16日(日)14:00〜16:00 |
| 場所 | ZOOMオンライン開催 |
| 対象 | ・医学生、看護学生、薬学生等の医療系学生 ・緩和ケアの教育に関心のある医療者 |
| 参加費 | 無料 |
| 内容 | 講師 安部 能成(ピース訪問看護ステーション・リハビリ研究ディレクター) ゲスト講師 梅崎 成子(作業療法士・東京大学病院リハビリテーション部) 藤田 曜生(作業療法士・九州大学病院リハビリテーション部) |
| 申込URL | https://x.gd/5Ao7G |
| お問い合わせ | 大学病院の緩和ケアを考える会事務局 info@da-kanwa.org |
![]()
| 第11回(2024年) | 緩和ケアにおけるリハビリテーション〜医療者に知ってほしい新たな視点〜 |
| 第10回(2023年) | 死を意識した患者の苦悩に向き合う〜スピリチュアルペインとはなんだろう?〜 「スピリチュアルペインとは」 「スピリチュアルペインとケア」 |
| 第9回(2022年) | 多職種で関わる看取りのプロセス〜「物語で学ぶ緩和ケア」を活用して 「看取りの作法」 「日本の医療者の意識調査を踏まえて」 |
| 第8回(2021年) | 多職種向け緩和ケア教育授業〜患者の語りから考える緩和ケア〜 【第1部】患者の語りと緩和ケアのポイント 【第2部】ディスカッション |
| 第7回(2020年) | 臨終時の緩和ケアとオンライン教育について医学や薬学部の教育経験をプレゼン 「死を通して生といのちを考える」 「死亡診断時の医師の立ち居振る舞い」 「臨終時の多職種の関わり」 |
| 第6回(2019年) | 第1部 プレゼンテーション 「死に向きあうことのできる 医療者教育(仮) 」 発表者:死に向きあう医療者の育成検討委員 第2部 ワーク「医学生が死に向きあうための授業作り」 成果物:緩和ケア臨床実習モデルプログラムVer.1・看取りのデモンストレーション |
| 第5回(2018年) | 第1部 講演「看取りの作法をどう伝えるか」 講師 林章敏 聖路加国際病院 緩和ケア科 部長 聖路加国際大学 がん看護学・緩和ケア 臨床教授 座長 黒子幸一 秦野メディカルクリニック 院長 第2部 ワーク「医学生が死に向きあうための授業作り」 |
| 第4回(2017年) | 第1部 〜ワールドカフェ「これからの医学教育に向けて新しい視点の創造へ」 「医学卒前教育としての緩和ケア教育内容の変遷とこれからの医療者に求められること」 第2部 講演「死を見つめる」 第3部 ワーク「患者の死に向き合うこと」をテーマとした授業作り |
| 第3回(2016年) | 多職種から学ぶ緩和ケア模擬授業 |
| 第2回(2015年) | ワンポイント授業コンテスト 〜これが私の授業です!パートⅡ〜 |
| 第1回(2014年) | ワンポイント授業コンテスト 〜これが私の授業です!〜 |
![]()
| 第10回(2013年) | とどけよう緩和ケアマインド |
| 第9回(2012年) | 心に残る緩和ケア講義の作り方 |
| 第8回(2011年) | 心をつかむ緩和ケア講義の作り方 |
| 第7回(2010年) | ひびけ医学生の心に 緩和ケア模擬授業 − 学んで伝える全人的ケア ー |
| 第6回(2009年) | とどけ医学生の心に 〜改定版「臨床緩和ケア」を活用した模擬授業〜 |
| 第5回(2008年) | 緩和ケアの模擬授業 パート3 〜緩和ケア講義を磨く〜 |
| 第4回(2007年) | とどけ医学生の心に 緩和ケア模擬授業 パート2 −学生の変容につながる講義の準備法、実施法、評価法− |
| 第3回(2006年) | 学習者中心の授業を作り上げよう |
| 第2回(2005年) | 医学生の緩和ケア教育のための教員セミナー |
| 第1回(2004年) | 医学生の緩和ケア教育のための教員セミナー |